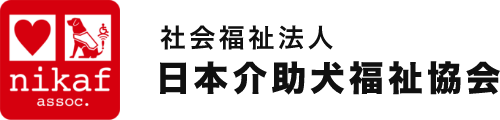介助犬という選択肢を
一人でも多くの方へ
日本介助犬福祉協会は、介助犬との生活を夢見る全国の希望者のために
「介助犬の育成と認定」や「介助犬の普及・啓発」を行う団体です。
日本介助犬福祉協会は、
厚生労働大臣から
指定された法人です
身体障がい者補助犬(介助犬、盲導犬、聴導犬)として育成された犬が他人に迷惑を及ぼさないことや適切な行動を取る能力があることを認定する機関として、厚生労働大臣に指定されています。
私たちが目指す未来
一人でも多くの身体障がい者が、
より良い人生を歩めるように
アシストする
身体障がい者の方々が介助犬と生活し、毎日笑顔で過ごせる未来を皆さまと
一緒に創りあげることであり、その未来の扉を介助犬が開き、
心のバリアフリー社会を創ってくれると信じて日々活動を続けています。
私たちの役割
介助犬と生きる
ライフスタイルを届ける
現在の日本では、介助犬との生活を選びたくても選べない方が多くいます。
私たちの役割は、1人でも多くの方が介助犬との生活を選び実現できるように
制度や仕組みを変えることです。
日本における介助犬の
課題と目指すこと
介助犬と生きるライフスタイルを届けるには、
現在の日本には制度上の課題があります。
活動の目標
1,000人の身体障がい者に、
介助犬を届ける
全国には約193万人の肢体不自由者がいると言われています。※1
このうち、日本における介助犬希望者数は約1000人は下らないということが
当会独自のリサーチによりわかっています。
しかし現実には、実働している介助犬の数は全国でたったの57頭です。※2
介助犬を希望するすべての人、つまり、1,000人の方に介助犬を届ける。
それが私たちの活動の目標です。
※1 2017年時点・国立研究開発法人情報通信研究機構より引用 ※2 令和3年11月時点
私たちの活動
1,000人の身体障がい者に介助犬を届けるために、国からの認可を受けておこなう訓練・認定に加え、一般の方にも介助犬の重要性を伝える普及・啓発活動もおこなっています。
-
介助犬の訓練
ユーザーと心が通じる介助犬を育てる活動です。
-
介助犬の認定
使用者と社会のために、介助犬の能力を見極めます。
-
介助犬の普及・啓発
介助犬の重要性を伝え、社会に広げる活動を行なっています。
活動紹介
理事長からのメッセージ
🐾介助犬使用者と介助犬の幸せを目指して
私、川﨑元広は2025年3月20日付で、社会福祉法人日本介助犬福祉協会の理事長を藤田英明前理事長より引き継ぎ、令和3年4月以来2度目の理事長に就任いたしました。
これまで、介助犬と共に生きる方々が自立し、笑顔を取り戻していく姿に深く心を動かされ、この活動に情熱を注いでまいりました。
しかしながら、日本における介助犬の認知度はいまだ十分とは言えず、その価値が社会全体に広く理解されていないのが現状です。
そこで、私たちは改めて「目指せ 介助犬1,000頭」という目標の実現に挑みます。今後10年以内に、現在の約5倍にあたる 280頭の介助犬が活躍する社会 を目指します。単純計算では、全国にある25の育成団体がそれぞれ毎年1頭ずつ介助犬を送り出せば達成できる数字です。
しかし現実には、継続的に活動できている団体は10団体前後にとどまっています。その背景には、制度上の課題や活動資金の確保の難しさ、さらには昨今の物価上昇など、さまざまな要因があります。
こうした状況を踏まえ、制度改革や支援体制の見直しも視野に入れながら、持続可能な介助犬育成の仕組みづくりに力を注いでまいります。
当協会では、皆さまのご支援のおかげで過去5年間に輩出した介助犬数は国内トップを誇り、毎年2〜4頭のペースで介助犬を送り出しています。
また、当協会の原点である「人と犬の共生社会の実現」という理念は、1999年に小さな任意団体から活動を始めた創設者・川崎芳子(母)から受け継いだものです。
社会のためにこの志をさらに発展させ、介助犬を必要とするすべての方々に寄り添う支援を提供してまいります。
これからも「ユーザーファースト」を信念に、丁寧で温かい支援を心がけながら、介助犬の普及と社会の福祉向上に尽力いたします。
皆さまの変わらぬご理解とご支援を心よりお願い申し上げます。
2025年3月吉日
社会福祉法人 日本介助犬福祉協会
理事長 川崎 元広
ご寄付のお願い
介助犬を一人でも多くの人に届けるため、
あなたの力を貸していただけませんか
政府や地方自治体に頼った現状の制度では、必要とする人に介助犬を届けることができません。新しい仕組みを私たちとつくりませんか。
法人としてできること
企業・団体として、介助犬を届ける
新しい仕組みに参加しませんか
一人でも多くの身体障がい者へ介助犬の選択肢を届けるために、企業・団体としてできる取り組みがあります。