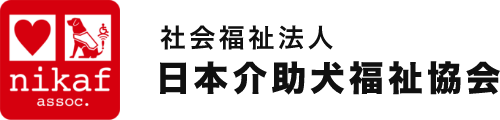PICK UP重要なお知らせ
ABOUT日本介助犬福祉協会について
介助犬とともに生きる
選択肢を届けるために
日本介助犬福祉協会は、介助犬との生活を夢見る全国の希望者のために
「介助犬の育成と認定」や「介助犬の普及・啓発」を行う団体です。
1,000人の身体障がい者に、介助犬を届けることを目標に活動を続けています。
PROBLEM取り巻く課題
届ける数に限界がある
官に頼った制度
日本における介助犬希望者数は約1000人いると推定されます。しかし、身体障がい者でもごく一部の人しかユーザーとなれません。
その背景には、行政の限られた補助金に頼った現状があります。
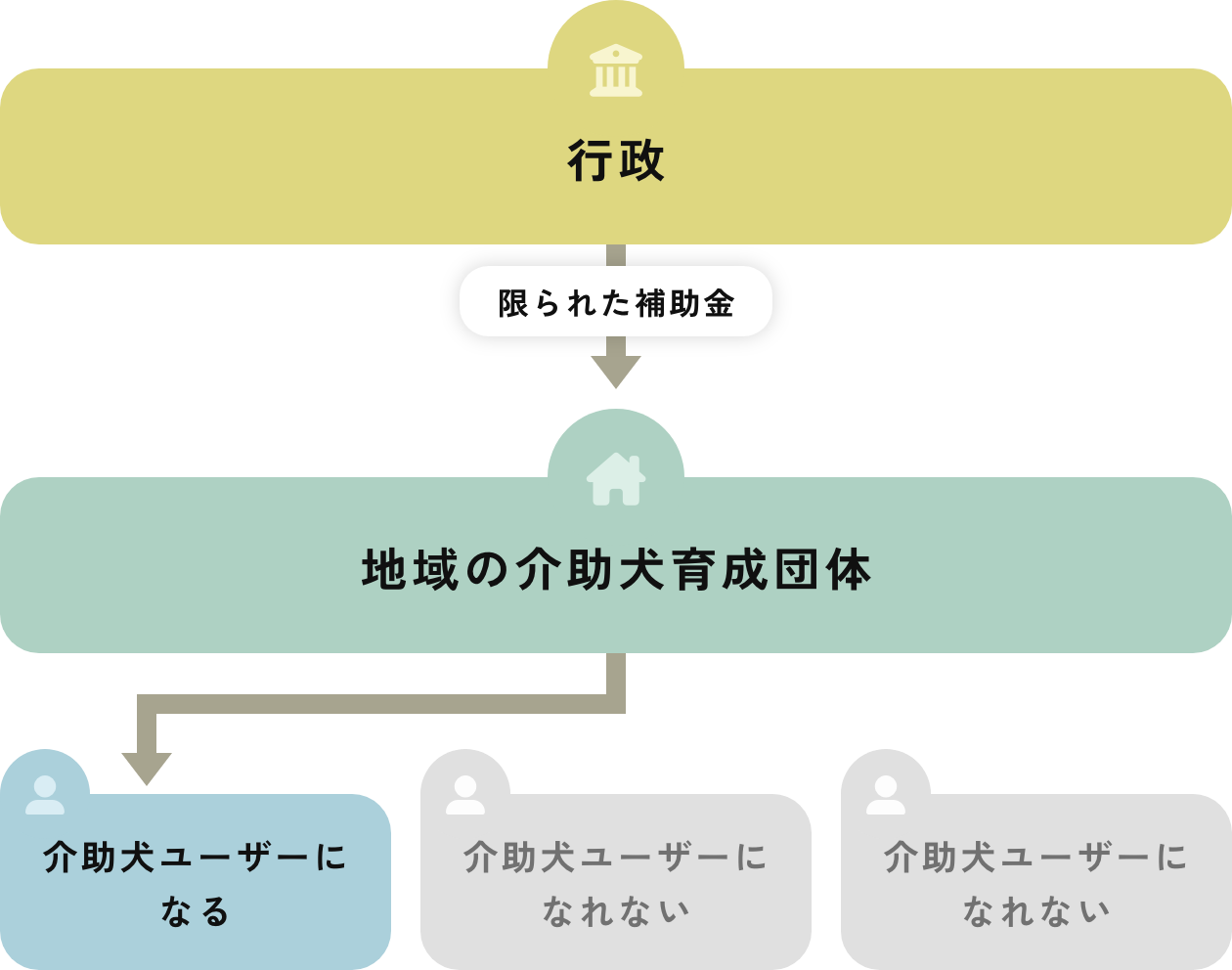
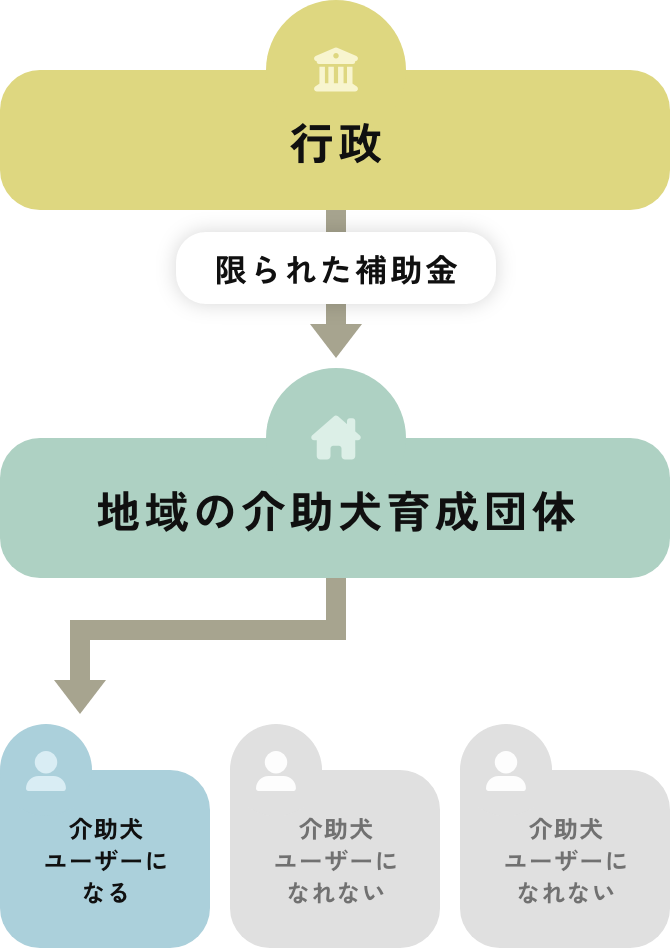
GOAL活動を通して目指すもの
介助犬を市民が育て届ける
仕組み「新・介助犬」
一人でも多くの方に介助犬と生きる選択肢を届けるには、官に依存することなく、民の力で伸ばしていく必要があります。
「介助犬=市民が育てる介助犬」となることを目指し、寄付による育成体制の構築をおこなっています。
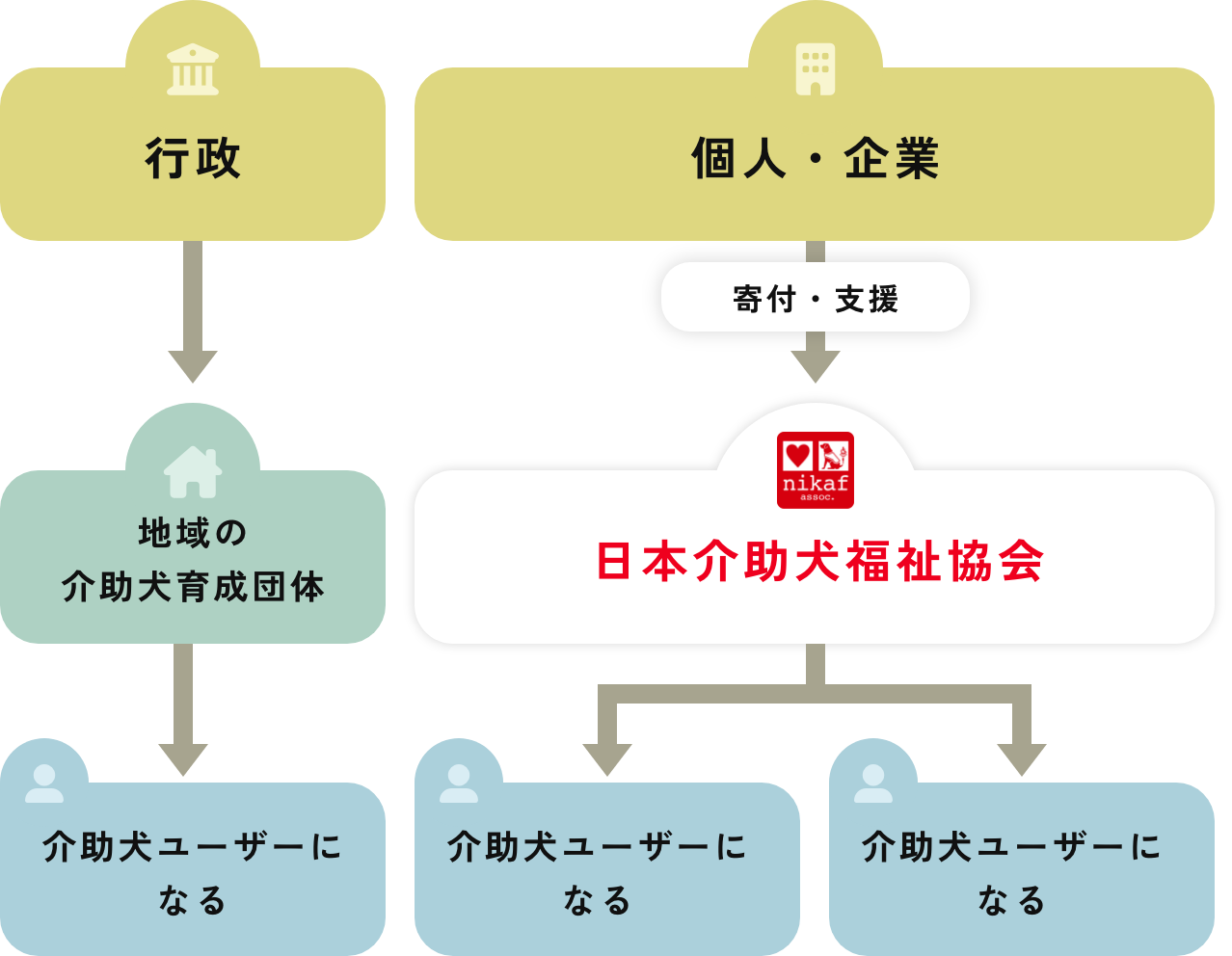
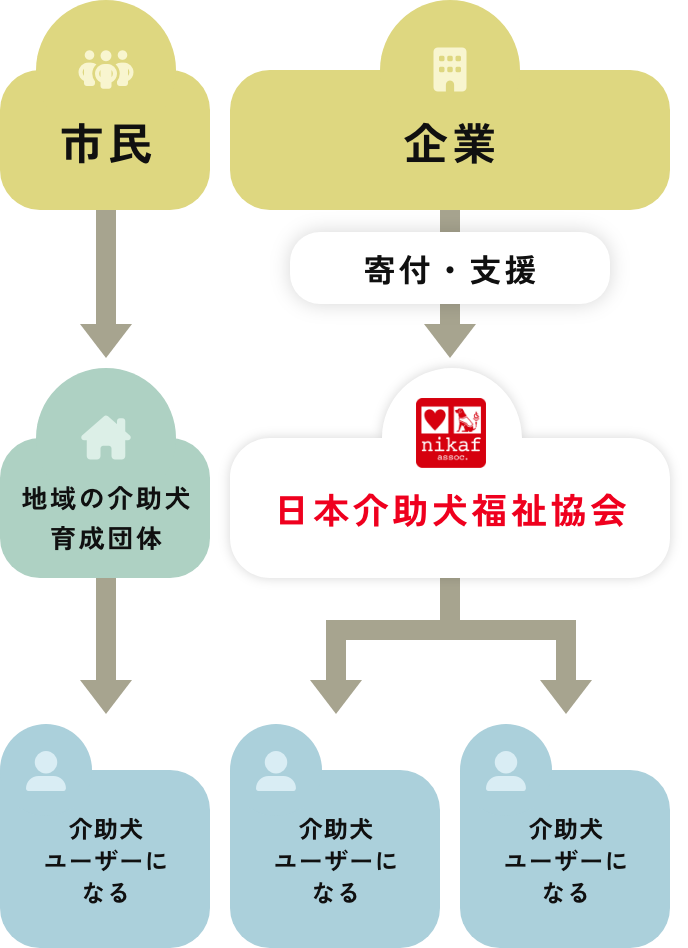
REPORT活動レポート
DONATIONご寄付のお願い
介助犬の仕組みを変えるために、あなたの力を貸していただけませんか
官に依存しない「市民が育てる介助犬」を実現し、
1,000人の身体障がい者に介助犬を届けるには、皆さまからのご支援が必要です。
介助犬の仕組みを変えるために、力を貸していただけませんか。